「和菓子」という言葉は、西洋の文化が取り入れられるようになった明治時代から使われるようになった言葉です。
日本文化の象徴ともいえる「和菓子」が、明治時代に、どのような場所で、どのようなものが作られ、人気があったのかを知ることができるのではないかと思います。
「和菓子」の歴史をお楽しみいただくのと共に、100年以上続く歴史ある老舗の和菓子屋さんが、伝統を継承していただいていることに感謝していただけたら嬉しく思います。
明治時代創業の老舗さんからわかること
明治時代から続く老舗さんが作る菓子の種類
明治時代から100年以上続いているお店さんには、餅、饅頭、羊羹、産地の果物を使った菓子といったそれぞれを専門で作られているお店さんが多くなります。
現在の和菓子やさんは、それらすべての商品取り入れているお店さんが多いですが、1つの商品に拘って作っているお店さんが多いようです。
もちろん、その1つの商品に拘っているわけではなく、如何にその時代にあった味に変えていっているということもあるのかと思います。
継承と時代の変化のバランスを上手く取り入れる努力をされているのが、長く続けていくことができる証拠なのでしょうか。
明治時代からある老舗さんの地域性
京都、東京は多く、お茶(茶道)が盛んな地域などにも多くあるようです。
明治時代の菓子の食べられ方
まだまだ街道などにある茶屋などで食べられていることが多いようです。
また、お伊勢さん参りだけでなく、各地の神社などにお参りに行く際の近くにある茶屋で食べたり、持ち帰ったりすることが多かったようです。
明治時代(1868~1912年頃)創業のお店
室町砂場
◆創業 明治2年(1869年)創業。
◆創業当時の商品 蕎麦。天ざる、天もり発祥のお店。
◆現在の商品 「蕎麦」「そばぜんざい」など。
◆現在の住所 東京都中央区日本橋室町。
「そばぜんざい」は、そば切りにたっぷりのこしあんがかかっているものです。温かいものと冷たいものが選べます。
伊豆河童(いずかっぱ)
◆創業 明治2年(1869年)。
◆創業当時の商品 ところてん(天草)。
◆現在の商品 ところてん、あんみつなど。
◆現在の住所 静岡県駿東郡清水町。
菓子舗 間瀬(ませ)
◆創業 明治5年(1872年)
◆創業当時の商品 菓子
◆商品の変化 昭和になって、あんぱん、アイスキャンディー。戦後、パン、飴、菓子。
◆現在の商品 白餡を中心とした新作和菓子。
◆現在の住所 静岡県熱海市。
永楽堂


◆創業 明治6年(1873年)
◆創業当時の商品 さくらもち
◆現在の商品 「長八さくらもち」など。
◆現在の住所 静岡県賀茂郡松崎町。
彩雲堂(さいうんどう)
◆創業 明治7年(1874年)。
◆創業当時の商品 菓子
◆商品の変化 一度絶えた「若草」を明治時代中期に復活させました。
◆現在の商品 「若草」など、和菓子全般。
◆現在の住所 島根県松江市。
鳴海餅本店
◆創業 明治8年(1875年)。
◆創業当時の商品 お餅、お赤飯、お菓子。
◆商品の変化 1915年に自動餅搗機(もちつきき)導入。
◆現在の商品 餅、赤飯、生菓子、カラフルなおはぎなど。
◆現在の住所 京都府京都市上京区。
青柳総本家
◆創業 明治12年(1879年)。
◆創業当時の商品 蒸し羊羹。
◆商品の変化 数年後にういろう。
◆現在の商品 ういろう。
◆現在の住所 愛知県名古屋市。
和菓処 大田屋
◆創業 明治13年(1880年)
◆創業当時の商品 餡
◆現在の商品 生どら「のっぽ」など、和菓子全般。
◆現在の住所 静岡県御殿場市。
中村軒
◆創業 明治16年(1883年)
◆創業当時の商品 饅頭、麦代餅(むぎてもち)
◆現在の商品 饅頭、麦代餅、おはぎ、団子など
◆現在の住所 京都府京都市西京区。桂離宮の真裏。
空也(くうや)
◆創業 明治17年(1884年)、上野にて創業。
◆創業当時の商品 最中
◆現在の商品 「空也最中」「空也餅」など。
◆現在の住所 東京都中央区銀座。
豆政
◆創業 明治17年(1884年)
◆創業当時の商品 砂糖豆、塩豆
◆商品の変化 明治20年、五色砂糖掛豆を考案(現在の夷川五色豆)
◆現在の商品 「夷川五色豆」など豆製品。
◆現在の住所 京都府京都市中京区。
浅草満願堂
◆創業 明治19年(1886年)
◆創業当時の商品 芋きん
◆現在の商品 「芋きん」、各種きんつば
◆現在の住所 東京都台東区浅草。他にも店舗あり。
風月堂
◆創業 明治19年(1886年)
◆創業当時の商品 羊羹
◆現在の商品 「八雲小倉」「黒小倉(冬季限定)」など
◆現在の住所 島根県松江市。
石鍋商店
◆創業 明治20年(1887年)
◆創業当時の商品 久寿餅、寒天、こんにゃく
◆現在の商品 久寿餅、あんみつ類、酒まんじゅうなど。
◆現在の住所 東京都北区岸町。王子稲荷神社近く。
こぎく
◆創業 明治20年(1887年)
◆創業当時の商品 菓子
◆商品の変化 明治43年にピーナッツ菓子「国の光」がロンドン日英博覧会にて金杯受賞
◆現在の商品 まんじゅう、ピーナッツ菓子、ベビーシューなど
◆現在の住所 静岡県浜松市中区神田町。
つるの玉子本舗 下山松壽軒
◆創業 明治20年(1887年)
◆創業当時の商品 つるの玉子(マシュマロの中に餡が入っているもの)
◆現在の商品 つるの玉子、きびだんご、調布など
◆現在の住所 岡山県岡山市北区。
風流堂(ふうりゅうどう)
◆創業 明治23年(1890年)
◆創業当時の商品 菓子
◆商品の変化 大正時代のはじめ、江戸時代のお菓子である「山川」を復刻。
◆現在の商品 「山川」「朝汐」「若草」など
◆現在の住所 島根県松江市。
竹風堂
◆創業 明治26年(1893年)
◆創業当時の商品 栗菓子
◆現在の商品 「どら焼山」、栗ようかん、栗かのこ、干菓子など
◆現在の住所 長野県上高井郡小布施町。
三条若狭屋
◆創業 明治26年(1893年)
◆創業当時の商品 細工菓子、飾り菓子
◆商品の変化 大正時代初期に「ちご餅」を創作
◆現在の商品 「祇園ちご餅」など
◆現在の住所 京都府京都市中京区。三条通り堀川。
羽二重餅総本舗 松岡軒
◆創業 明治30年(1897年)
◆創業当時の商品 「羽二重餅」(明治38年発売開始)
◆現在の商品 「羽二重餅」「羽二重もなか」「羽二重どら焼き」など
◆現在の住所 福井県福井市。
大黒屋鎌餅本舗
◆創業 大黒屋鎌餅本舗は明治30年(1897年)創業。それ以前にも鞍馬口にある茶店で出されていました。
◆創業当時の商品 「鎌餅(かまもち)」
◆現在の商品 「鎌餅」「懐中汁粉」「最中」「でっち羊羹」
◆現在の住所 京都府京都市上京区。出町柳。
なごみの米屋
◆創業 明治32年(1899年)
◆創業当時の商品 栗羊羹
◆現在の商品 「栗羊羹」「ぴーなっつ最中」など
◆現在の住所 千葉県成田市。成田山表参道。
阿左美冷蔵 金崎本店
◆創業 明治32年(1890年)
◆創業当時の商品 天然氷
◆現在の商品 かき氷
◆現在の住所 埼玉県秩父郡皆野町金崎
松月堂
◆創業 明治32年(1899年)
◆創業当時の商品 栗せんべい
◆現在の商品 栗せんべいなど
◆現在の住所 山梨県南巨摩郡富士川町。
出町ふたば
◆創業 明治32年(1899年)創業。
◆創業当時の商品 豆餅
◆現在の商品 「名代豆餅」など
◆現在の住所 京都府京都市上京区。出町柳。
村岡総本舗
◆創業 明治32年(1899年)
◆創業当時の商品 練羊羹
◆現在の商品 「小城羊羹」「シベリア」など
◆現在の住所 佐賀県小城市。
塩津小饅頭老舗
◆創業 明治33年(1900年)
◆創業当時の商品 酒饅頭
◆現在の商品 「酒饅頭」「栗入り皮蒸し羊羹」など
◆現在の住所 静岡県静岡市葵区。
舟和
◆創業 明治35年(1902年)
◆創業当時の商品 芋ようかん
◆現在の商品 「芋ようかん」「あんこ玉」など
◆現在の住所 東京都台東区浅草。
岡萬本舗
◆創業 明治35年(1902年)
◆創業当時の商品 「か津ら ふぢ餅」
◆商品の変化 昭和58年より洋菓子部門開設
◆現在の商品 「ふぢ餅」「お堰の小舟」「バターサンド」
◆現在の住所 徳島県西郡石井町。
松栄堂
◆創業 明治36年(1901年)
◆創業当時の商品 「あめ玉」や「味噌パン」などが中心の駄菓子屋に近いお店でした。
◆商品の変化
2代目が、練った梅を団子の中に入れ、塩漬けと蜜漬けした青紫蘇で包んだ「田むらの梅」を考案。その後、団子の中に、はちみつを加えてとろっとした摺りごまを入れた「ごま摺り団子」ができました。
◆現在の商品 「田むらの梅」「ごま摺り団子」など
◆現在の住所 岩手県一関市地主町。一関は餅の町として有名。
にわかせんべい本舗 東雲堂
◆創業 明治39年(1906年)
◆創業当時の商品 「二〇加煎餅(にわかせんべい)」
◆現在の商品 「二〇加煎餅(にわかせんべい)」
◆現在の住所 福岡県福岡市博多区。
太平堂
◆創業 明治40年(1907年)
◆創業当時の商品 パン、お菓子
◆現在の商品 「まほろばの月」「裾花」「レモンケーキ」など
◆現在の住所 長野県長野市。
松月堂
◆創業 明治40年(1907年)
◆創業当時の商品 栗生菓子
◆現在の商品 「栗苞(くりづつみ)」「栗羊羹」「栗きんつば」など
◆現在の住所 岐阜県中津川市。
玉井屋本舗
◆創業 明治41年(1908年)
◆創業当時の商品 「登り鮎」
◆現在の商品 「登り鮎」
◆現在の住所 岐阜県岐阜市。
有職菓子御調進所 老松
◆創業 明治41年(1908年)
◆創業当時の商品 古来より朝廷に伝わる儀式・典礼に用いる菓子、茶道に用いる菓子
◆現在の商品 「夏柑糖」、薯蕷まんじゅうなど
◆現在の住所 京都府京都市上京区ほか
中村製餡所
◆創業 明治41年(1908年)
◆創業当時の商品 あんこ。
◆現在の商品 つぶあん、こしあん、白あんなど。
◆現在野住所 京都府京都市上京区一条通。北野天満宮近く。
浪花家/浪花家総本店
◆創業 明治42年(1909年)、東京麹町にて「浪花家」を創業。
◆創業当時の商品 たいやき たいやきは、この店が起源とされます。
◆現在の商品 たいやき、やきそば、お汁粉、かき氷、あんみつなど
◆現在の住所 東京都港区麻布十番。
現在は、暖簾分けした兄弟子さんが「浪花家総本店」を麻布十番で営業されています。
柚餅子総本家 中浦屋
◆創業 明治43年(1910年)創業。
◆創業当時の商品 「丸柚餅子」
◆現在の商品 「丸柚餅子」ほか。
◆現在の住所 石川県輪島市。
現在の状況につきましては、ぜひ下記HPをご覧ください。何の関係もない私が言うのはおかしいことかもしれませんが、中浦屋さんの1ファンとして、皆様にもご協力お願い申し上げます。
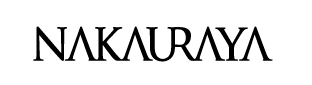
明日はどんな手仕事する?
明治時代になると、西洋の文化が取り入れられるようになったこともあり、菓子の世界も幅が広がり、流れも変わってきます。
西洋のお菓子を「洋菓子」というのに対し、日本のお菓子を「和菓子」といったのもこの頃からです。
餅やだんご、饅頭、羊羹、柿や栗菓子などを店先で食べる茶屋タイプが多かった江戸時代に比べると、持ち帰ったり、内容のよりグレードアップしたもの、より個性的なものなどが見られるようになっています。
地域性としても、江戸時代には、江戸や京などを中心とし、お茶文化が発展していた地域や宿場町などに多かったお店も、明治時代になると、より広い地域にお店が分散されてきました。
とはいえ、明治時代とは、今から100年以上前のこと。100年以上前、道具なども今ほどのものがない時代に、これだけの内容のものが作られていたことに脱帽します。また、それが100年以上続けられていることにも感嘆します。
伝統を継承していってほしいと願うばかりです。
それでは、最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。
明日が素敵な1日になりますように。
老舗和菓子店の関連記事
◆「老舗和菓子店①江戸時代より前に創業のお店」の記事はこちら ↓↓↓

◆「老舗和菓子店②江戸時代創業のお店」の記事はこちら ↓↓↓

◆「老舗和菓子店➃大正時代創業のお店」の記事はこちら ↓↓↓

和菓子の関連記事
◆「和菓子の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子①和菓子の種類」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子③地域別の和菓子」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「和菓子⑥和菓子の歴史」の記事はこちら ↓↓↓

季節の手仕事の関連記事
◆「季節の手仕事カレンダー」はこちら ↓↓↓

◆「食材別の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「暦としつらえの季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「お花の季節の手仕事」のまとめ記事はこちら ↓↓↓

◆「おすすめの食材店と旬の食材探しで訪れたい道の駅」のまとめ記事はこちら ↓↓↓









コメント